ゲンドウは、謎の人物と電話していた。使徒の事、「例の計画」について、シナリオ通りに進めることを密談する。
ミサトの家でペンペンと朝食を取るシンジ。いつものように寝坊してきたミサトは、朝からビールを飲んで至福を得る。
シンジは、ミサトが「その歳で未だに一人の理由」が分かった気がすると言って茶化す。今日のミサトはシンジの進路相談について学校へ行くと言った。
学校に到着したミサトは男子生徒から大人気。シンジは「みんなあの人のだらしなさを知らない」というが、うらやましがるトウジとケンスケに突っ込まれてしまう。
シンジは、エヴァの存在に思いを巡らせる。血の臭いのするエントリープラグ。それなのに「落ち着く」のはなぜか。結局、自分はまだ何も分かっていないことに苛立つ。
シンジはジオフロント深部へ降りてゆくデッキの上で資料を眺めていた。その横では、リツコとミサト、オペレーターの伊吹マヤ、日向マコトがNERVの抱える予算問題について話している。
会議に向かうため、ゲンドウは機上の人となっていた。ゲンドウの隣に腰を下ろした男は、サンプル回収の修正予算があっさり通ったことを伝える。どうやら「使徒はもう現れない」というのが、人類補完委員会の論拠らしかった。
さらに、米国を除く全ての理事国がエヴァ6号機の予算を承認したことを伝える。「我々の道は使徒を倒す意外にない」とゲンドウが言うと、「セカンドインパクトの二の舞はごめんだ」と男が答える。
リツコは「セカンドインパクト」についてシンジに説明する中で、事実は往々にして隠蔽されるものだと言う。15年前、人類は「最初の使徒」を南極で発見するが、その調査中に原因不明の大爆発が起きたことを明かす。
リツコは、NERVやエヴァが存在するのは、サードインパクトを未然に防ぐためだとシンジに伝える。
ミサトの家でペンペンと朝食を取るシンジ。いつもと様子の違う背筋を伸ばした格好で現れたミサトを見て言葉を失うシンジ。仕事で旧東京まで行くというミサトを見送る。
A HUMAN WORK
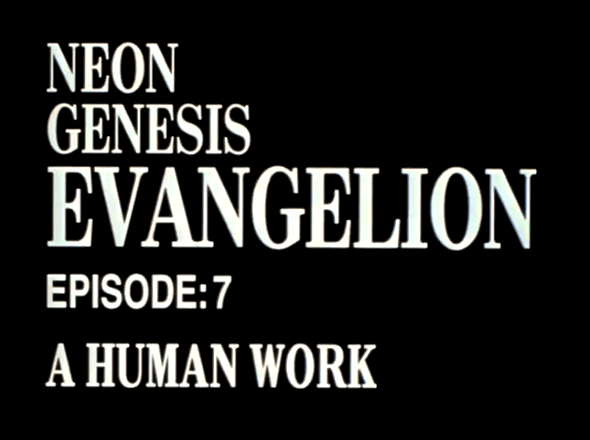
かつて花の都と呼ばれた大都会、旧東京に訪れたミサトとリツコ。そこでは日本重科学工業共同体による「JA完成披露記念回」が行われていた。
今回、会場に集まった多くの関係者の前で、ある〝兵器〟の実演が披露されるという。壇上で話す執行役が質問を受けると、リツコが挙手し問題を指摘。執行役は、むしろエヴァの問題点を上げ、それと比較してNERVを揶揄する。
実演会で〝JET ALONE〟――通称JAの起動テストが開始される。JAは問題なく順調に歩行を進める。しかし、途中でアラームを検知。緊急停止の信号を受け付けず、制御不能に陥ってしまう。
歩行を止めないJAは、管制室を踏み潰し直進し続ける。このまま稼動を続ければ炉心融解の危険が迫る中、執行役はお手上げ状態だった。
見かねたミサトは独断で行動することを宣言。エヴァ初号機とシンジを現場に運ぶよう要請する。止めようとするリツコの言葉にミサトは耳を貸さない。事故収束を最優先に強行するミサトを見て、折れた執行役は緊急停止パスワードを伝える。
〈希望〉――それで全てのプログラムが消去されるはずだった。
現場に到着した初号機とシンジを乗せた輸送機の中で、ミサトは今回の作戦内容を指示する。それは自分の犠牲を顧みない危険なものだった。そのため、ミサトの身を心配するシンジだったが、ミサトは「やれることはやっておく」と言って作戦を決行する。
輸送機から切り離されたエヴァ初号機は、ボディスーツを着たミサトを手に乗せてJAの背中を追ってゆく。難なく機体を捕らえ、ミサトをJAのハッチ付近へ送り出す。
ミサトがJAのハッチを空けると、内部は高温になっていた。進行するJAを力ずくで止める初号機。稼動時間は限られている。制御室を探し出し、コントロールパネルにパスワードを入力するミサト。しかし、何度パスワードを入力しても表示されるのは〝ERROR〟の赤い文字。プログラムが改竄されていることに気づいたミサトは、イチかバチかの行動に出る。
ミサトは力ずくで制御棒を押し出そうとする。しかし、人の力ではどうすることもできない。その時、プログラムが作動しJAは緊急停止する。
爆発は免れた。安堵するシンジや現場関係者たち。しかし、ミサトは分かっていた。奇跡は用意されていた――誰かの手によって。
NERV本部。今回の件についてゲンドウに報告するリツコ。「例の計画」はシナリオ通り遂行された。一部の例外はあったにせよ。
ミサトの家でペンペンと朝食を取るシンジ。またいつもの調子に戻っているミサトを見て、浮かない顔をする。JAの一件で見直したはずの女性は、どこへいってしまったのか。迎えに来たトウジとケンスケに、シンジは愚痴をこぼす。しかし、友人から意外な言葉を返されて、シンジは気づくことになる。
他人の俺たちには決して見せない本当の姿。
「――それって、家族じゃないか」
