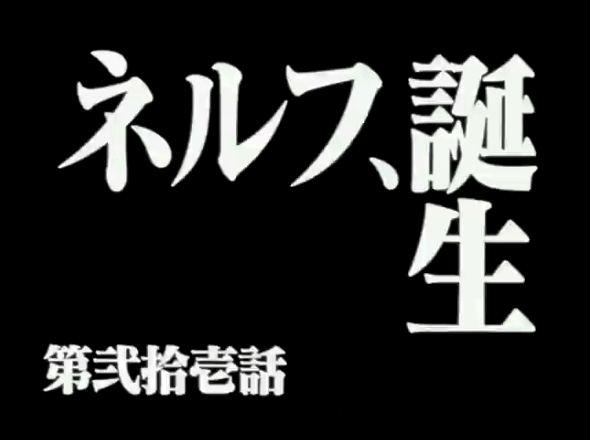寂れた田舎道の公衆電話で加持はミサトに電話を掛けていた。しかし、そこに聞こえてきたのは留守番電話のメッセージだった。〝NERV〟と書かれたカードに目を落として「最後の仕事か、まるで血の赤だな」と加持は吐き捨てる。
冬月が拉致されたという知らせを受けて、ミサトは諜報部員に目を付けられていた。この件の首謀者、加持リョウジとの関係を疑われてのことであった。ミサトは無駄な抵抗はせずに、NERVのカードと銃を差し出し連行される。
後ろ手に縛られた冬月は、キール議長の手荒な歓迎に苦笑いする。キールは目的遂行のためには手段は選ばないとほのめかす。冬月は、そこに現れた他の面々が委員会ではなくゼーレということに、意外だったと反応して見せる。
「我々は、新たな神を作るつもりはないのだ」
ゼーレは、ご協力を願いますよ、〝冬月先生〟と言って要求を悟るように促す。
1999年 京都。
大学教授時代の冬月は、飲みの席で「碇という若者が君に会いたがっている」と伝えられる。興味を持った冬月は、かつての碇ユイと出会う。
再び 2015年。
S2機関を取り込み、絶対的存在を手にしたエヴァンゲリオン初号機の件について、ゼーレに問われる冬月。神は不要とするゼーレ。ゲンドウの手に〝神〟が渡ることを恐れるゼーレは、彼のことを指して「信用に足る人物かな?」と冬月に問いかける。
再び 1999年
冬月がゲンドウに抱いた第一印象は「嫌な男」だった。当時のゲンドウは、酔って喧嘩をするなど悪い噂の耐えない人物だった。冬月の噂を耳にしたゲンドウは、一度会ってみたかったという理由で、留置されていた警察から身元引受人として冬月を指名したのだった。
ある日、冬月はゲンドウと付き合っていることをユイに告白されて驚く。しかもゲンドウは、ユイの背後にある組織〝SEELE〟に近づくために、ユイと接触したのではないかという噂が流れていた。そして、20世紀最後の年に「セカンドインパクト」は起こった。21世紀最初の年は、地獄しかなかったと振り返る冬月。
2002年、南極大陸を調査するツアーで冬月に接触するゲンドウ。そこで、ユイと結婚し、「碇」という姓に変わったことを告げる。ユイは一緒ではないのかと聞く冬月に、ゲンドウは、彼女も来たがっていたが、今は子供がいると伝える。ゲンドウが関わっている組織、ゼーレの悪い噂に言及する冬月。奇麗事では生き残れないと言うゲンドウは不適な笑みを浮かべていた。
2015年 NERV本部・第4隔離施設
暗い部屋で膝を抱えるミサト。暗いところはまだ苦手と、セカンドインパクト時の記憶を蘇らせる。
2002年 南極調査船・第2隔離施設
葛城調査隊の生き残りとして保護された幼いミサトと接触した冬月は、そこで彼女の心の傷の深さを知る。当時、冬月はセカンドインパクト時に出現した〝光の巨人〟の謎について追っていた。国連は、メディアに対して「セカンドインパクトは大質量隕石の落下によるもの」と正式発表した。あからさまな情報操作で真実を隠蔽しようとする思わくの裏に見え隠れするゼーレ、そしてキールという存在。冬月は真相を知りたくなった。その先に、「碇ユイ」の名前があるとも知らずに。
2003年 箱根 国連直属 人口進化研究所
研究所の所長になっていたゲンドウに対して、冬月はなぜ巨人の存在を隠すのかと詰め寄る。事件の前日にゲンドウが運良く葛城調査隊の現場から引き揚げたこと、それと同時に全ての資料も引き上げられていたことを挙げ、偶然ではない何かがあるのではないかと冬月は考えていた。
セカンドインパクトの真相を暴くために、冬月はゼーレのことや死海文書を公にするとゲンドウに伝える。しかし、全く動じないゲンドウは、冬月にあるものを見せたいと言って地下に案内する。
「我々ではない、誰かが残した空間」に潜って行くゲンドウと冬月。ゲンドウは、「人類がもてる全てを費やしている施設」へと冬月を案内する。施設に着くと、そこにいたのは赤木ナオコだった。彼女は、生体コンピュータの基礎理論を模索中だと言い、それを〝MAGI〟と名付けると冬月に説明する。冬月を「見せたい物」へ案内するため、ナオコはそこにいた制服姿の少女に「リツコ、すぐ戻るわ」と言って席を外した。
冬月は目を疑った。目の前に探していた巨人の姿があったからだ。光の巨人のことをゲヒルンでは「アダム」と呼んでいると説明するナオコ。しかし、ここにあるのはオリジナルではなく「アダムより人の造りしもの、エヴァ」だと言う。ゲンドウは、アダム再生計画を現在遂行中で、通称〝E計画〟の雛形であるエヴァ零号機を見せるために冬月をここへ呼んだのだった。「神のプロトタイプか」そうつぶやく冬月に対して、ゲンドウは「俺と一緒に人類の新たな歴史を作らないか」と言った。
He was aware that he was still a child.
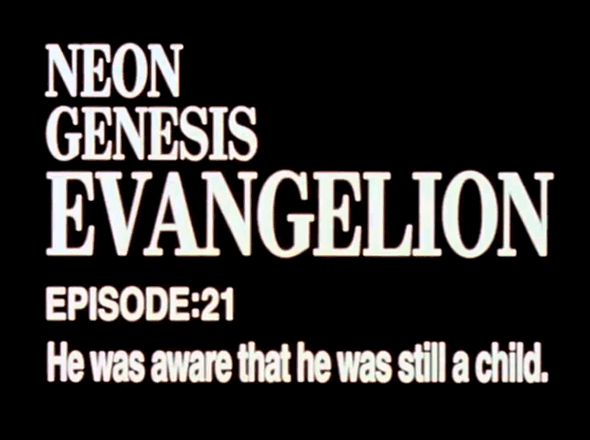
2015年 NERV本部
エヴァ初号機を見つめていたリツコは、マヤの呼びかけで我に返る。葛城さん今日見ませんねというマヤの言葉に、リツコは「そうね」とだけ答える。
2005年 長野県 第2新東京市
第2東京大学の構内でミサトと知り合ったリツコ。母親の権威の影響で友達作りに苦労していたリツコをよそに、ミサトは屈託なく話しかける。そんなミサトの事をリツコは、母・ナオコへの手紙で綴っている。そこでミサトから加持を紹介されたエピソードを交えて。
2004年 箱根・地下第2実験場
実験試料に目を落とすナオコに、無邪気な笑顔を見せる幼いシンジ。場違いな子供がいることに顔をしかめる冬月。私が連れてきたんですとユイが謝る。しかし彼女は、シンジに明るい未来を見せておきたいという言葉を最後に、不慮の事故で帰らぬ人となってしまう。ナオコは、その日を境にゲンドウが変わったとリツコへの手紙に綴っている。その後、ゲンドウはキールに対して人類補完計画を進めることを提唱したと冬月に伝える。
2008年
車窓を眺めるリツコ。MAGIの基礎理論を完成させたことに祝いのことばを述べ、自分もゲヒルンへの正式入所が内定したことを伝える手紙をナオコへと送る。リツコはE計画勤務となった。ジオフロント内に発令所の躯体が完成したために見学に訪れるが、そこでゲンドウとナオコの知られざる関係を目撃してしまう。
2010年 ジオフロント 人口天蓋部 下層第2直援エリア(予定地)
ゲヒルン本部を足元に見下ろすゲンドウは、少女にそのガラス越しの景色を説明していた。そこにナオコとリツコが現れると、「知人の子を預かっている」と言って、綾波レイを紹介した。レイを見たナオコは、そこにユイの面影を感じ取る。気になったナオコは、レイについて調べを進めると、レイに関する全ファイルは抹消済とされていた。
S.C.MAGI SYSTEM 完成
完成したMAGIを見下ろすナオコとリツコ。「科学者としての私」「母親としての私」「女としての私」。三人の私がせめぎあっているのだとナオコは説明する。リツコは、久しぶりにミサトに会って飲むのだと言って先に上がる。ミサトはゲヒルンに入り、ドイツの第三支部勤務に勤務していた。
ナオコの元へ「道に迷った」というレイが現れた。私と一緒に出ようと提案するナオコに向かって、レイは「大きなお世話よ、ばあさん」と冷淡な言葉を口にする。それを聞いて耳を疑い驚くナオコに向かって、更に「一人で帰れるから放っといて、ばあさん」とレイは続ける。
「怒るわよ、碇所長に叱ってもらわなきゃ」と声を震わせるナオコに向かって、所長がそう言ってるのよ、とレイは告げる。ばあさんはしつこいとか、ばあさんは用済みだとか。レイの言葉で頭が真っ白になるナオコ。
「あんたなんか死んでも代わりはいるのよ、レイ。私と同じね」
気が付くと、ナオコの両手はレイの細い首に掛かっていた。レイの両手は既に力を無くして垂れ下がっていた。絶望したナオコは、発令所の高所から身を投げ、自らその役目を終えた。
キール・ローレンツを議長とする人類補完委員会は、調査組織であるゲヒルンを即日解体。全計画の遂行組織として特務機関NERVを結成した。そして、ゲンドウや冬月、以下関係者はそのままNERVへと籍を移した。
2015年
拘束された冬月を解放する加持。彼はゼーレを裏切った。その行動は命取りになると忠告する冬月に対して、自分の中の真実に近づきたいだけなのだと加持は答える。その頃、拘留されていたミサトも解放された。問題は解決したと言う諜報部員に対して、ミサトは加持の所在を確認する。しかし、存じませんとだけ言われて彼の身を案ずる。
誰かを待つ加持の元に歩み寄る人の気配。
「よぅ、遅かったじゃないか」と言った加持は、銃声に包まれた後、消息を絶った。
疲れきったミサトはドアを通って「ただいま」と言った。加持の安否を気に掛けて、テーブルに座って顔を伏せる。ふと電話機の方に目を向けると「留守番電話」のランプが点滅していることに気が付く。ミサトは、恐る恐る再生のスイッチを押すと、そこに流れてきた聞き覚えのある声に身を硬くする。
「葛城、俺だ。多分この話を聞いている時は、君に多大な迷惑をかけた後だと思う。すまない。リッちゃんにもすまないと謝っておいてくれ」
「後、迷惑ついでに俺の育てていた花がある。俺の代わりに水をやってくれると嬉しい。場所はシンジ君が知ってる」
「葛城、真実は君とともにある。迷わず進んでくれ。もし、もう一度会える事があったら、8年前に言えなかった言葉を言うよ。じゃ」
メッセージが記録された時間を機械音声がアナウンスする。ミサトはそのまま泣き崩れる。
「バカ……あんた、ほんとにバカよ……」
物音に気づいたシンジはイヤホンを外してキッチンを覗いた。肩を震わせて声を上げるミサトを見て、シンジは無言で部屋へ逃げ込んだ。シンジは、ベッドに埋もれながら、こんなとき何も言えない子供なんだということを思い知る。